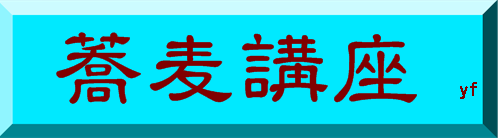���c���c��ł����̍���
�z��
[Top]
�@���Ε�100%�ł́A���n�̂Ȃ��肪�キ��Ƃ�����̂ŁA�ʏ�͏�������z�����܂��B���̏��������A���킹���A�Ȃ����ȂǂƉ]���܂��B
�@���ǂ�Ő��������悤�ɁA�������̃O���e���̏���������āA���ΐ��n������܂��B�i���Ε��́A�ޗ��̃y�[�W�ŏЉ�����������́u�X���v�Ɓu�҂�����݁v����сu�ŕ��v��ʐM�̔��œ��肵�܂����j
�@�u�X�ȁv�̓����́A�F���ŔS�肪���Ȃ��A����͎ア�����ꊴ���悢���Ƃł��B�u�҂�����݁v�͂��̋t�ŁA���҈꒷��Z�Ƃ������Ƃ���ł��B�D�݂�ړI�ɉ����đI�����Ă��������B
�@
�@1�|�C���g�@�ŕ��i�������j�́A�蕲�i�Ă��ȁj�Ƃ������܂��B���ǂ���ł́A���������n�ׂ͂����̂ŕЌI���i�n�鏒�b���j��ŕ��Ɏg���̂���ʓI�ł��B
�@�����ł́A�e�ڂ̂��Ε����g���̂����ʂł��B���Ε��́A�S�肪���Ȃ����炳�炵�Ă���̂ŁA�ŕ��Ƃ��Ă̎g���Ղ��͕ЌI�����D��Ă��܂����A���Γ���n�ޏꍇ�͕K�v�ł��B�@
�@
�@���Ε��Ə������̔z�������ɂ́A���܂�͂���܂��A���I�ɂ͕���i�̕\���Ɋւ���K��ŁA���Ε�30%�ȏ�z���������̂��h���h�Ɖ]�����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���Ε��́A�҂�����݂̕����S�����𑽂��܂ފW�Ő��n���q����₷���̂ŁA�ŏ��͂������Ɏg���܂��B
�@�������́A���͕��܂��͒��͕��i���ʕ��j�̂ǂ���ł��g���܂����A�H�����玄�͒��͕��A��������ǂ�p�����D���ł�����g���܂��B�����ł́A���{�����́u�߂v��u���ʂ��e�v���g���܂��B�������A��ʂɂ͋��͕����g���̂����ʂł��̂ŁA���߂Ă̕��͋��͕�����n�߂ĉ������B
�@��ʂɎ�ł����ł́A���Ε������A�������̓i�ɂ͂��j�����嗬�̂悤�Ȃ̂ŁA����ʂ̖ڕW�Ƃ��܂��B�������ŏ��́A���Ε��܁A�������܂̓����ŃX�^�[�g���邱�Ƃɂ��܂��傤�B����ł��A���ǂ���Ɋr�ׂāA���n���ア�̂Ō����ĊȒP�ł͂���܂���B
�@�܊��̔z���ŁA�����̗v�̂����߂��Ƃ���ŁA���Ε��̔z�����ꊄ�������ĉ������B�u�v�ɓ��B���āA�Ɋ��ꂽ��A���Ε�90%�ɁA�����čŏI�͋��ɂ̐��s��100%���ɒ��킵�܂��傤�B
�@
�@1�|�C���g�@���ΐ��i�̕i�����e���u�`�����v�Ɣz�����ʼn]���̂���ʓI�ł����A���Ε����̂̕i�����e�̕����{�������Əd�v�ł��B����́A���Ε��̕i���ɂ͑傫�ȕ������邩��ł��B�������̏ꍇ�́A�i���i�O���[�h�j�������D���ܗʂ�0.3�`0.5%���x�̂��̂Ȃ̂ɑ��āA���Ε��ł�0.4�`2.0%���x�̂��̂܂ł���A�ǂ��I�Ԃ��Ŗ����H�����傫���ς��܂��B�܂��A����ɉ����Č��̌������̕i�������e������ł��B
�@�]���Ė˂Ƃ��Ă̂��́A�z��������������悢�Ƃ������Ƃł͌����Ă���܂���B
�@���Ɖ]���\���́A�]�ˎ��ォ��̂��̂ł����A���̈Ӗ��ɂ͏����������āA���Ε������������Ƃ����̂͂��̓��̈���ł��B�]���āA���Ε��Z�����l�Z���Ƃ͉]���܂���B
�@
�@���ۂ̗ʂł����A���Ε��A���������킹��500g���x�����Αł��Ƃ��Ă͓K�ʂ��Ǝv���܂����A�����܂ł͌��\���s�������̂ŁA���Ε��ʂɂ��Ȃ����߂ɂ��A���킹��300g�ŃX�^�[�g����Ƃ悢�ł��傤�B�]���Č܊����̏ꍇ�́A���Ε�150g�Ə�����150g�ɂȂ�܂��i����ł��A�O�l�ŐH�ׂ�Ȃ�K�ʂł����A��l�ł͑��߂��܂��j�B
�@�����ʂ́A45%���x�ł����A���Ε��̐����A�z���ʁA�����x�ɂ���Ă��Ȃ�ς��܂��B��ʂɁA���Ε��̔z����������ɂ�āA�܂����O���[�h�̂��Ε����g���ꍇ�ɂ͉����ʂ����₵�܂��B�]���āA�ŏ��͗l�q���݂�K�v������܂����A�����̏ꍇ�͎�肠�����u�҂�����݁v�̏ꍇ��43%�A�u�X���v��45%�������Ă݂܂��傤�B�ŏI�̐��n�̍d���́A�ŏ��͓�炩�߂̕�������ł����A�v�̂���������������o���邾���d�߂ɂ��ĉ������B
�@�H���́A���ł͎g��Ȃ��̂����ʂł����A�������̔z���������ꍇ�i�܊��ȏ�j�͎g�������������ł��傤�B���n�����܂�A�ׂ�����}���܂��B�g�p�ʂ́A�S�ʁi300g�j�ɑ���2%�i6g�j�����x�ł��B
�v��
[Top]
�@�v�ʂ́A���ǂ�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�m���ɍs���ĉ������B�����́A���ǂ���Ɋr�ׂēK�������̕��������̂ŁA���m�Ȍv�ʂ����߂��܂��B
�@�����ŁA���������i���j����ꍇ�A���߂͉����ʂ����m�ɒ͂߂Ȃ��̂ŁA���͑��߂Ɍv�ʂ��Ă����A�ꊄ���x�c���ĉ����ėl�q���݂�A�Ɖ]���̂���ʓI�ł��B�������A���߂Ă̐l�ɂ͗l�q���܂��͂߂܂��A�v�ʎ�`�̂��̍u���ł́A���߂���v�ʂ������͑S�ʓ���邱�Ƃɂ��܂��B
�@������300g(100%)�Ƃ��āA������150g�i50%�j�A���Ε��i�҂�����݁j150g�i50%�j�Ɛ�129g�i43%�j�𐳊m�Ɍv�ʂ��ĉ������B�H���́A�����ł͎g���܂���B
�@�����������ʁA���n���d������炩�����̔��f�́A�����o����ς߂킩��܂����A�˖_�ʼn������Ƃ��ɉ����Ђъ��ꂷ�邩���Ȃ����̏������悢�d���ł��B��炩������ꍇ�́A���͉�����1�`2%���炵�Ă��������B
�@�v�ʂ��������肵�Ă���A�K�������ʂ͂����ɒ͂߂܂��B
����
[Top]
�@�v�ʂ������Ε��y�я�������⿂����Ƃ̍l�����́A���ǂ���ł̏������̏ꍇ�Ɠ��l�ł��i��ł����ǂ�̍����P�̒����Q�Ɓj�B���Ε��ɂ��Ă͏o������ł����A��x��⿂��Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B
�@���������g���W�ŁA�~���͉����͒g�߂Ďg���܂��B���n���₽����(25���ȉ�)�O���e���̓����������A���n�̌q���肪�����Ȃ�܂��B���ǂ�Ɠ����悤�ɁA�O���e�������L���ɂ��邽�߂ɂ͐��n���x��27���ȏオ�]�܂����̂ł��B
�@�������A���̏ꍇ�́A���ɑłĂ�悤�ɂȂ�A�q���̕⏕�̕K�v�x�������Ă���̂ŁA�ώ������Ȃ����邱�Ƃ�D�悵�āA���n���x���߂ɗ}���邱�Ƃ͉\�ł��B�A���A�Ċ��ɂ͐������g���Ɛ��n���x27���ȏ�ɂȂ�A������5���̗␅���g���Ă����n���x��24�`25�����x�ł��B�X�ɁA�����①���Ă����21�`22���܂ʼn�����܂����A20���ȉ��ɂ���͓̂���悤�ł��B
�@�H�����g���ꍇ�̗v�̂́A���ǂ�̏ꍇ�Ɠ����ł��B
����
�Ɲs��
[Top]
�@��^�̃{�E���i�s�˔��j�ɁA�v�ʂ������Ε��Ə����������āA�y�����������܂��B����Ɍv�ʒ������Ă��������������܂����A���ő~�������Ȃ��疜�ՂȂ������s���n��悤�ɏ����������܂��B���߂���w�ő~��������ƁA�G�ꂽ��w�ɂ��Ε�������t���ė��Ƃ��̂���J�ł��B�ꉞ�A���i�ʐ^1�j�ŕ��ɐ������܂�����Ɏ���g���A�₽���w�ɒ���t�����Ƃ͂���܂���B
�@�������I������A���̏��Ő��n������Łi�ʐ^2�j���݂ق����悤�ɂ��āA�葁���S�̂��ψ�ȉ�����ԂɂȂ�悤�ɂ��܂��B���Ƃ����Ă��܂��B
�@�S�̂��A�����Ƃ�d�������ɂȂ�����A���ɐ��n��͂ނ悤�ɂ��Ĉ�̉�ɂ܂Ƃ߂܂��i����j�B�܂Ƃ܂������ŝs�˂܂����A���̂�����͂��ǂn�̎�s�˂Ɠ��l�ŁA����Ő��n���x���āA�E��Ő��n��܂�Ԃ��ĝs�˂܂��B
 |
 |
 |
 |
| �@�P�@�������鍬���� |
�@�Q�@�葁������ |
�@�R�@��������s�˂� |
�@4�@�ւ��o�����` |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�͂��ׂē̂����̎��̂��́j
�@
�@���ǂ�ƈ���āA���n�̏n�����s��Ȃ��̂����ʂŁA���̂܂ܝs�˂𑱂��Ă��\���܂��A���Ε��͗����e�����������̒��ɟ��ݓ�̂ŁA�����Ɲs�˂����_�i�e�s�ˁj��10�����x�Q�����Ă���ēx�s�˂�̂����ʓI�ł��B
�@���n�́A���ǂ�Ɋr�ׂ�Βe�͂����Ȃ��s�˂₷���̂ŁA�S�̂����炩�Ȍ����тт�܂ŁA��������s�˂ĉ������i�ʐ^�R�j�B���n���Ȃ��牽�x���܂�Ԃ��ĝs�˂܂����A�T�O��`�P�O�O��̝s�˂��ꉞ�̖ڈ��ł��B
�@�s�˂̎d�グ�ɋe���݂����āA��ᰂ��Ԗ͗l�ɒ����ɏW�߂܂��i�ʐ^�E�j�B�e���݂́A�܂�Ԃ������������āA���n�������Ԃ�5,6��s�˂č��܂�
�@
�@���ʂ̎菇�F���[����i������j�[�s�ˁ[�e���݁[�ւ��o���|�n�����[�ۏo���[
�@���J�Ȏ菇�F���[����[�e�s�ˁ[�i�Q�����j�[�s�ˁ[�e���݁[�ւ��o���[�n�����[�i�Q�����j�[�ۏo���[
�@�@
�@�Ō�ɁA���n�𗼎�ɋ���ō��E�ɓ]�����Ȃ��琶�n���ɋ�C���c���Ȃ��悤�ɁA���n��ᰑ����i��悤�ɂ��āi�w�摤�A��ǂ���ł��悢�j�Aᰑ���������o���[���i�C���j��ɂȂ�悤�ɐ��`���܂��i
�ւ������ʐ^4�j�B�o���[����ɓZ�߂����n���A�ŕ���U�����̂���ŁA�ւ������ɂ��ďォ���ʼn������ĉ~�Տ�ɐ��`�i�n�����ʐ^6�j���܂��B�Q����������ꍇ�͂����œ���܂����A����Ȃ��ꍇ�͒����ɖ˖_�ɂ�鈳���ɓ���܂��B
�@�������̔z���������A�H�����g�����ꍇ�́A�n�����̌�10�`30���ԐQ����������悢�ł��傤�B
�@
�@1�|�C���g�@�������̔z�������Ȃ��ꍇ�i�[���j�ł��A��ʘ_�Ƃ��ĝs�˂����n�͍d���Ȃ��Ă���A�Q�����ɂ���č\�����ɂނ̂ŁA�����O�ɏ����Q������Ή����₷���Ȃ�܂��B
�@�Q�������ԂƊɘa�̌��ʂ̊W�ł����A�ɘa��p�͎��ԂƋ��ɒ������܂��B�n���̖ړI�ł��鐶�n�̊ɘa�́A���߂�10���͒����I�Ŋɘa�ʂ��傫���̂ŒZ�����Ԃł��[���L���ł��B
����
[Top]
�@���n��s�ˏI�����璼���ɉ�����Ƃɓ��邱�Ƃ��o���܂����A������30�����x�Q���������Đ��n�������������Ƃ���ʼn��������A���H���̒��܂��������ł���悤�ł��B�Q���������邩����Ȃ����͍D�݂ɂ��܂��B�����ɓ���܂łɎ��Ԃ��Ƃ��́A�����h�~�i�n�����ʂ�����j�̂��߁A�Z���Ԃł��r�j�[���܂ɓ���Ă����ĉ������B
�@�����菇�͂��ǂ�̏ꍇ�Ɠ����ł����A���ǂn���e�͓I�ō����Ȃ̂ɑ��āA���ΐ��n�͑Y���I�ő@�ׂł������r�Ȉ��������Ȃ��悤�ɋC��t���܂��B
�@�悸��Łi�ʐ^5�j�y���ۂ������i�Q����������ꍇ�͂����Łj�A���ɖ˖_�ʼn~�Տ�ɐ��`������i�ʐ^6�j�A�y���蕲��U���āi�ł������āj�˖_�Ɋ����t������A�ŏ��Ɋp�������s���܂��B
�@�p�o���́A�{�����̑O�ɁA���n���l�p�ɐ��`����H���ł��B�˖_�Ɋ����ς��āA�㉺�A���E�ɉ����v�́i���ǂ�̉����Q�Ɓj�͂��ǂ�������ł����A�͂̊|����͑S���قȂ�܂��B����̂Ђ�Œ��������ォ��y���}�����A�O���ɓ]�����܂��B
�@
 |
 |
 |
| �@5�@�悸��Ŋۂ��n�̂� |
�@6�@�˖_�Ŋۏo�� |
�@7�@�p�o���I���߂ɍL���� |
�@�����߂��Ă܂��O�ɓ]�����܂����A���̓�����Q�`�R��s���܂��B���ǂn�̏ꍇ�́A���n�̒e�͂��������߁A�p���o��̂ł����A���ΐ��n�͑Y���I�Ȃ̂ŁA�p�o���͗e�Ղł��B
�@�ł����́A���������n������t���Ȃ����x�Ɍy���s���Ă��������B�p�o���̍H�����I������A���n���̂��̑Ίp����ɍL���܂��i�ʐ^7�j�B�ŏI�̑傫���������菬�����l�p�`�̐��n���o���܂��B
�@�������̔z�������Ȃ��قǁA��������ڂ��c��A���݂��s�ψ�ł�����A���̎��_�ŁA�L�������n�̏�Ŗ˖_��]�����Č��݂ƌ`�𐮂��܂��B�����ŁA���łɖڕW�̌��݁i���݂͌�������̂ŁA���ʂ͍L�������ʐςŔ��f���܂��j�ɂȂ�A���̂܂��̕��ɓ���܂��B
�@��ʂɂ͓K�X�ɑł������Ė{�����ɓ���܂��B�㉺�A���E�́A�˖_�������ς��Ă̈����͊p�o���Ɠ��l�ł����A�]�����͗���𒆉����痼�[�ֈʒu�����炵�Ȃ�s���܂��B���ǂ��悤�ł����A�\�t�g�^�b�`�Œ��J�Ɉ����܂��B
�@�Ō�̎d�グ�́A�p�o���Ɠ��l�ɁA�L�������n�̏�Ŗ˖_��]�����čs���܂��B���̍Ō�̒����́A���n���̋�C�����o������ŁA�˖_����������}���ē]�����ĉ������B���̖˖_�̓]��������ŁA���n�̌q���肪��������A䥂ł����̌������ƐH�����ŏI�I�Ɍ���܂��B
�@�ŏI�̐��n�̌��݂�1.5mm����x���ڕW�ł����A���S�̊Ԃ͍L�������n�̖ʐςŌ��������܂��B�T�C�Y�́A300g���n�̏ꍇ50�����l�p��ڕW�ɂ��Ă��������i500g���n�̏ꍇ�́A����������70����*60�������x�ɉ����܂��j�B
�@�P�|�C���g�@���n�ʂƉ��������n�̌��y�іʐς̊W���͉��L�̂悤�ɂȂ�܂��B
�@[���n�ʁ����n�ʐρ����݁����n��������d]�@��̎l�p��ł͌�����300g���n�̏ꍇ�̌v�Z��
�@[��������������n��429g=�ʐς���2������0.15cm*��d1.2]�@����A�l�p�̈�ӂ�49cm�ƂȂ�܂��i�~�`�̏ꍇ�͒��a55cm�ɂȂ�܂��j�B���ۂɂ́A�ۂ݂�тт��l�p�Ɏd���̂ŁA49�`55�����̒��Ԃ̑傫���Ƃ��܂��B
�@�Ȃ��A���|����d1.2�͌o���l�ŏɂ���đ����ς��܂����A���l�Ƃ��Ďg���Ă��������B
���n�̐܂��݂ƕ��
[Top]
�@�����I������A���̂��߂ɐ��n��܂��݂܂��B�܂��݂̏ꍇ�́A�ł����������Ղ�g���܂��B
�@�悸�����ɐ܂��݂܂����A���n�̍��������ɏ[���ɑł������i�ʐ^�W�j�A���n�̉E�[�����������č��[�ɍ��킹�܂��B�ʐ^�ł́A��Ǝ҂����������ɂ���̂ŁA��ʂ̉E����Ǝ҂̍��ɂȂ�܂��B
�@300g���n�͏������̂Ŏ�Ŏ����グ�Ĉ�������܂����A500�����n�ŏ������z�������Ȃ��ꍇ�͑傫����Ɍq������ア�̂ŁA��ňꕔ������������Ɛ��n����܂��B���̏ꍇ�͉E�[������˖_�ɏ悹�āA�˖_�Ő��n�S�̂������������ė��܂��i�ʐ^�W�j�B�i�����I�������n���A�̂���ɍL����Ƃ��ɁA������E�֍L���A�Ō�̈ꊪ������˖_�Ɋ������܂܂ɂ��Ă����A�˖_���Ǝ����Ă���ΊȒP�Ɉ�������܂��j
 |
 |
 |
| �W�@���n���E���獶�܂�d�˂� |
�X�@�������ɂQ��܂�d�˂� |
�P�O�@��� |
�@���ɁA�܂������ɐ܂��݂܂����A���̎��͉��[�������ď�[�ɍ��킹�܂��B�ł����͂��̏ꍇ���A���n�̏㑤�����ɂ����Ղ�|���܂��B
�@�Ō�ɁA�������ł������ĉ��[�����[�ɔ����ɐ܂�d�˂܂��B����Ő��n�͔����d�˂����ƂɂȂ�܂��i�ʐ^�X�j�B�@
�@���Ԕ����Ă����āA�E�[�����Ő�܂��B�v�̂́A���ǂ�̏ꍇ�Ɠ����ł��i���ǂ�ҎQ�Ɓj�B�蕝�́A�D�݂ɂ��܂���1.4mm�`1.5mm���W���ł��B�悭������g���āA�����ɑO�ɉ����o���悤�ɐ�܂��B
�@���ΐ��n�͌q���肪�キ�A���ǂ�Ɋr�ׂď��Ԕ�����������ł����A���炭������Έ�����悤�ɂȂ�܂��B
�@7�`8cm��i��A���̓s�x�A��̕��Ő��������d���āA�ʂ̔┠�i���M�j�Ɉڂ��܂��i�ʐ^�P�O�j�B�Ȍ�A���̈�d������P�ʂƂ��Ĉ�����悤�ɁA�d�Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��܂��B
䥂ŁA����
[Top]
�@��肵����A�Ԃ�u������䥂łɓ���܂��傤�B�傫�߂̓�ɂ����Ղ�̓������܂��B���̂��߁A���n�������n�߂�O�ɁA����Ɋ|���Ă����܂��B
�@���̗ʂƂ��̗ʂ̊W�ł����A�q���̎ア���قlj��x�̒ቺ����������̂ŁA���̗ʂQ�g�ɑ��Đ����̗ʂ�200g�ȉ��ɗ}���܂��B�Η͂��W���܂����A���𓊓���30�b�ȓ��i�x���Ƃ�60�b�ȓ��j�ɍĕ�������悤�łȂ��Ƃ����܂���B�Η͂��キ�āA�ĕ����Ɏ��Ԃ��|����悤�ł�����A���̓����ʂ����炵�ĉ������B䥂Ŏ��Ԃ�2�`3���ł�����A�ƒ�ł͑傫�ȓ�ɂ����Ղ�̓��ŁA��l���i120�`150g�j����䥂ł邱�Ƃ������߂��܂��i�����Ă���l���܂łł��j�B
�@�����A�ꃖ���ɂ����܂�Ȃ��悤�ɁA�ς�ς�ƑS�̂ɍL����悤�ɓ������܂��B�����āA�ĕ������n�܂�܂Ŕ��Ȃǂő~�������Ă͂����܂���B
�@�������n�܂�����A�y�����ł��������ĉ������B䥂Ŏ��Ԃ͎c�菭�Ȃ��̂ŁA�ɒ[�ȉΗ͒����͂����A�����オ���Ă�����A�����������܂��B�������̗ʂ́A�����������͈͂ŏ��ʓ���܂��B�����ɂ����܂����A�������Ă���2�`3�����x���K��䥂Ŏ��Ԃł��B���̎��ԓ��ł܂�䥂ł���Ȃ��i�d���j�悤�ł���A������������ƍl���Ă��������B
�@���Ԃ�������A䥂ł���Ԃŋd���āA�\�ߗp�ӂ��Ēu�����������{�E���Ɉڂ��܂��B�{�E���̒��ŁA���Ɨ�p���s���܂����A����Ń{�E���̒ꂩ��䥂�����ɕ������銴���ōs���܂��B�����܂��g�����ꍇ�́A������x�A�������{�E���ɂ����ڂ��āA���l�̑�������܂��B
�@�Ō�ɁA���x�������������{�E���ɂ����ڂ��āA�K�����x�ɂ����d�グ�܂��B�K�����x�ɂ͍D�݂�����Ǝv���܂����A���̂��E�߂�20���ł��B15���ȉ��ł͗₽�����āA���̖����킩��܂���B
�@�K�����x�̂����A��œE��ŖԂɎ��A������āA�e��ɐ�����܂��B�i�ʐ^�́A�҂�����ݕ����g�������s�˂̏\�����ł��j
�@���𖡂������A�Ō�ɂ��Γ����y���݂܂��傤�B���Β����ɁA���Γ��������Ղ����Ė��키���Γ��ɂ́A����䥂œ��Ƃ���̎|�݂���̂ƂȂ�����������������܂��B���Ƌ��ɁA����̐^����������ʂł�����܂��B�i���́A�L�b�R�[�}���́u�{��v�����ǂ�ɂ����ɂ��g���Ă��܂��j
����
[Top]
�@���Ε��܊��̂��ŏ\�����h�Ȃ������������o���܂����A��͂�����o���Ȃ��Ƃ����łĂ�Ƃ͉]���܂���B����g���C���܂��傤�B
�@���Ε��Ə������ƕ�����300g�ŁA�����ł͓ł�����A���Ε�240g�A������60g�ɂȂ�܂��B
�@�������̔z�������Ȃ��̂ŁA���Ε��ɂ��S��C����������悭�A�ޗ��Ő��������悤�ɃO���[�h�̍������Ε��i��V���A�X�����j�́A�ŏ��͔����������悢�ł��傤�B�܂ŗ���ƁA�������͌q���̕⏕�ŁA�q���̎���͂��Ε����̂ɂȂ�܂��B�������̌q���Ɋ��҂��߂��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
�@�����ʂł����A�����z���ł����Ε��̐����ɂ���ĉ���́i5%�ȏ�́j��������悤�ł��B�̏ꍇ�́A�u�҂�����݁v���g���ꍇ46%�A�u�X���v�̏ꍇ48%���x�ł��B��x���܂�A��͓��������ʂł���܂��B
�@����́A���Ε��͏��������́u�҂�����݁v�ł�����A�K���ȉ����ʂ�46%�ł��i���������ł͂���܂���j�B�v�ʂ�300g��46%��138g(ml)�ɂȂ�܂��B
�@ �����ȍ~�́A��L�̌܊����Ɠ����ł��B�������g���������̗ʂ����Ȃ��ƁA�q���肪�ǂ����Ă��キ�Y���������Ȃ�̂ŁA�˖_�ł̈����ȍ~�̍H���ł́A��蒚�J�ȃ\�t�g�^�b�`��S�����܂��B
�@���n�̌q����̕⋭
�@���n�̌q��������߂�ɂ́A���Ε��̈ꕔ��M���ŝs�˂�A�R���̂��艺�낵���g���A�C���̕z�C�ۂ��g���ȂǁA���낢��ȍH�v������܂��B�������A�҂�����݃��x���̂��Ε��ł���A���܂łȂ���ʂȂ��Ƃ͂��Ȃ��Ă����Ƃ��ł��܂��̂Ńg���C���ĉ������B
�@
�\������
[Top]
�@��ł������ɂƂ��āA�Z�p�I�ȋ��ɂ̖ڕW�́A�Ȃ�Ƃ����Ă�100%���Ε��ł̎�ł��ł��傤�B����́A�����������Ƃ͕ʂ̎����̖��ł��B
�@���������g��Ȃ��\�����́A�O���[�h�̍����������Ε��ō��ꍇ�͏�L�̂悤�Ɍq����⋭����K�v������܂����A�u�҂�����݁v���x���̔S�����𑽂��܂ނ��Ε��ł���A���ŝs�˂邾���ō�邱�Ƃ��o���܂��B
�@�\�������A�̂����Ɋ���Ă���A�����ē���͂���܂���B
�@�g�����Ε�100%�i300g�j�ɐ�48%�i144ml�j�������A�葁�������Đ��n���܂Ƃ߂܂��B�܂Ƃ߂����n����ŗ���܂����A���n�͌q���肪�ア�̂œ̂Ƃ�������w�ɒ���t���܂��B����t���h�~�̂��߁A�Ƃ����萶�n�Ɍy���ł������ĉ������B
�@�������͓����Ă��܂��A��������s�˂Ă��������B�r���ŐQ������������ʂ́A�O�q�̒ʂ�ł��B���n���ł����牄���ɓ���܂��B��͍��܂Œʂ�ł����A�q����͎ア�̂ŎG�Ɉ����Ƃ����ɐ�܂��B
�@�����A䥂ŁA�������A�אS�̒��ӂōs���Η��h�ȏ\�������o���オ��܂��B�������A���ꂪ�����������Ɖ]����ΕK�����������ł͂���܂���B�g�������Ε��̃O���[�h�̖�������A�o�������̐F�͏���������ꂽ���Ɋr�ׂ�ƍ����A�H�������\���\�������̂ł��B
[Top]